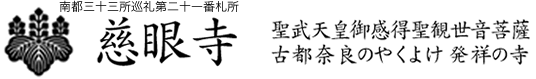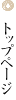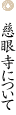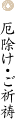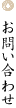レビュー『虚構推理』
久しぶりに寝る間も惜しんで、電車の中では駅に着くのを望まぬほどに、待ち合わせの喫茶店でも待ち人が遅刻するのを望むほどに、没頭してミステリを読みました。快作です。『虚構推理』。
この作家を語る上で、私がいつも思うのは「快作を創る人。ただし、それどまりな人」ということです。私はこの作家が大好きなのですが、同時に限界も感じています。しかしおそらくは、作家自身がその限界を熟知している。わざとやっている。そしてそれを以て任じている。そういう気がしています。「快作は生むが傑作は生まない、確信犯的な快作家」というのが、この作家への正当な評価なのではないかと思いますし、そこが私が彼を好きな理由です。
作者「城平京」氏は、言うまでもなく「平城京」をもじったペンネームの作家です。私とこの作家の作品との出会いは随分昔です。大学時代研究室の本棚整理をしていたところ、『名探偵に薔薇を』という文庫本が置いてあり、誰の持ち物かと聞くと誰も知らないと言いました。おそらくは卒業した誰かのものかと思われましたので、2週間放置した後、私のものになりました。たいして話題にもならなかった作品ですが、「奈良市出身 大阪市立大学卒」という、会ったことはないけれど、自分と思いっきりかぶるプロフィールの作者のこのミステリに、読み始めたときから引き込まれました。
ミステリに何を求めるか?というのは様々な意見がありましょう。トリックの見事さ、キャラクターの魅力、設定の妙など、色々あります。人里離れた古い因習のうずまく山村の、三代前からの暗く陰鬱な人間関係だけでご飯三杯いける人もいれば、乾いた理系文体にエキセントリックなアニメ的登場人物が大好きな人もいるでしょう。城平京はキャラクターを作り上げることに全力を注ぐタイプの作家だと思っています。
トリックももちろん駆使するのですが、それはもう薬物反応がどうとか、電車の時刻表がどうとか、密室がどうとか、そういうのは、最低限の「ありうるかもね」「バカバカしいけど、まぁアリかな」くらいの水準しか求めません。それよりはむしろ、ミステリの中の最大のフィクションである「名探偵」という最も不合理な存在を、いかに魅力的に作り上げるか、そこに彼の最大の関心事がある気がします。それはもう筆をとって文字を書く、などという生易しいものではなく、ほとんど「彫刻」と言いたくなるほどの力を込めて、鑿を打ち、『名探偵』という名の厳粛な像を彫り上げていきます。
彼の彫り上げる像はいつも厳粛です。
孤高にして、理想をどこまでも追求し、弱音を吐かない。心にたくさんの傷を負いながらも、決してそれに負けない。
それが最も端的にあらわれた『名探偵に薔薇を』において、彼の描く「名探偵であること」そのものは、決して名誉なことでも誇らしいこともなく、ただただ「真理」を追い求める存在です。そして、「そうであり続ける」ことは実は決して居心地のいい場所ではなく、常に大きな傷を負ってしまい、真実から目を背けたくなるような、そんなつらい「ありかた」です。「名探偵」は「職業」ではない。職業であればやめることができる。
そうではなくて、彼にとっての「名探偵」は、ほぼ「宿命」と同義なのです。
「自分が自分であり続ける」ことがそのまま「名探偵であり続けること」です。そして、人は常に自分であり続けるほど、強い存在ではない。常に状況や事情や感情に応じて、よく言えば「臨機応変」に、撓み、歪み、歪んでどうにか「世間」と「他人」に折り合いをつけて生きていきます。
だが「名探偵」は違う。
「名探偵」は常に「真理」だけを追います。「正しいこと」を「明らかにすること」だけを追い求めます。その結果、多くの人を不幸に陥れることになろうとも、それによって自分が大きく傷ついても、前に進み、「真理」を晒し続けねばならない。この「ねばならない」が、彼の描く名探偵のあり方に共通することなのだと思います。自らに課せられた運命を受け入れ、ただしそれが引き起こす結果にかかわらず、ただただ真っ直ぐに自分が「やらねばならない」ことを、行う。「他の誰もができないし、やらないのなら、自分がやらなくて、誰がやるのか」。結果ではなく義務に対する崇高なまでの決意が作品全体に基調として存在します。
繰り返しますが、それが最も先鋭的に表出したのがデビュー作『名探偵に薔薇を』でした。いわゆる大作でもない、話題になるわけでもない、大掛かりなトリックもないし、映像化してもたぶん盛り上がらない。地味なんだけど、妙に印象に残る。ミステリを読んだというよりは、悲しい詩を読んだような、そんな気がしてとても切ない作品でした。
それ以後、漫画原作の方に舞台を移されたと聞いて、残念がっていた私は、城平京の作品をチェックするのを怠っていました。4年も前にこんな本が出ていることも知らずにいた、不真面目なファンでした。ところが先日、新聞の片隅に『虚構推理』が文庫化されるという宣伝を見つけ、その日のうちに本屋に走り、以後、貪り読んでしまった次第です。以後、ネタバレありますので未読の方は注意。
前置きが非常に長くなりましたが、この『虚構推理』、『名探偵に薔薇を』と共通する部分もありますが、真逆に見える部分も多くあります。全体としての世界観は一気にファンタジーの、それも極北のような妖怪モノになっています。完全なファンタジーの世界で、論理だけを武器に、現実と嘘のせめぎあいを裁定する仲裁者であり巫女、それが本作品の「名探偵 岩永琴子」です。
「妖怪、言説、虚実」というキーワードだけでも、「京極夏彦?」としか思えない丸かぶりな設定なうえに、出てくる妖怪や神話の神がまたまた「アレ?これ京極作品に出てたよね?」というものばかりなので、コレはたぶんわざとやってんじゃないの?と思わないでもないのですが、印象としては案外真逆な作品になっています。試みとしては非常に面白い快作でした。
京極作品は、その有名な「「この世には不思議なことなど何もないのだよ」という言葉がすべてをあらわすように、怪異を言説によって解体する物語であり、それは同時にこの作品の時代設定とそのまま重なる「近代化」「脱魔術化」をも意味しています。いわば、「現実」の側に足を踏ん張って、「言説」の力で「不思議」を解体していくのが京極作品。
それに対して、『虚構推理』の岩永と九郎は、完全な怪異の世界の住人。岩永は「ひとつめいっぽん足」のあやかしたちの「知恵の神」、九郎は「くだんと人魚の肉を喰らった不死身のバケモノ」という設定です。まず、このおよそミステリに似つかわしくない設定をまるごと受け入れることから我々始めなければならない。その結果、よくあるミステリの目撃者のあるなし、物的証拠のあるなしなどの、地道で、確実で、でもちっとも面白くない要素を、すべて無視することができるようになります。なんてったって、岩永が命じれば、あやかしが見張って目撃証言を持ってきてくれたりするわけでから。証拠探しとか無意味なんです。
ですので、この物語は、「何が真実か」を問う物語ではない。完全に理屈の外にある「人外の者」が、世の中の秩序を乱すような「虚構」に対し、より穏当な結果を生む「別の虚構」でもって立ち向かうという、「虚をもって虚を制する」物語なのです。
つまり前提として、そこに「真理」と「虚構」の対立やヒエラルキーは存在しない。あるのは虚構Aと虚構Bの並立です。どこにも絶対的な位置にある特権的な「真理」は存在しない。ただ、虚構Aと虚構Bを分けるのは、どちらが支持されるか、市民権があるか。説得力があっても面白くなければ支持されないし、荒唐無稽で何の証拠も必然性もなくても人がそれを面白がれば、現実化する。何度も作中で喩えられる民主主義の議会やネット上の掲示板と同様です。デマゴーグであっても民意は民意。その場でウケればいいのです。「電車男」という、ネット掲示板から派生して、映画やドラマにまでなって消費し尽くされた事象がありましたが、「電車男」と「エルメス」が現実に実在するかどうかなんて、もはやどうでもいいのです。そんなものとは全く関係なく、「電車男」という「物語」にはリアリティーがあり、その意味では「電車男」は実在しています。
京極堂の「不思議なものなどない」というテーゼに対し、京極作品内では堂島大佐という「不思議でないものなどない」というアンチテーゼを提示する悪役がいますが、『虚構推理』では、「面白ければいい」という、京極作品のリングごとひっくり返すような壮大な「破格」を行っています。
とは言え、だから城平京が京極夏彦よりすごい!という気はありません。むしろ逆です。「ポストモダン」なんて「モダン」があってはじめて成り立つ奇策です。奇策はどこまで行っても奇策。『虚構推理』は京極作品の壮大なオマージュであり、パロディーであり、「本歌取り」です。断じて「パクり」というような志の低い作品ではありませんが、あくまで京極作品が分厚い新書を分厚く並べてくれたからこそ、それを蹴飛ばしてひっくり返すという遊びができたわけです。「城平京は快作家ではあるが、傑作は生めない」と私が主張する根拠はまさしくこの点にあります。おそらく本人が一番それをわかった上で、それを忠実に自分の作家性として認識していると私は思っています。
と、同時に、私は、『虚構推理』をただの京極作品のパロディーに終わる作品とは思っていません。オタク受けするエキセントリックな美少女に萌え萌えするだけの作品でも断じてない。
そこにはデビュー作から通底する「自分の宿命との戦い」というテーマが、変わることなく輝いているように思います。
「他の誰もがそれを行わないなら、なぜ自分がそれをしなくてはいけないのか」
普通の人はそう考えます。
ただ一人、「名探偵」と「神」になることを引き受けた者どものみが
「他の誰もがそれを行わないなら、なぜ自分がそれを逃れることができようか」
と、自らの運命を引き受ける、崇高な姿がそこにはあります。
妖怪たちの頼みを迷わず聞き入れ、自らの一部を捧げて「神」になった少女。
その妖怪を喰らわされて、「バケモノに恐れられるバケモノ」になった青年。
どちらもその異常な運命に対し、まるで怯むことなく、受け入れつつ、それが招く結果に絶望することも、諦めることもなく、その運命のもたらす結果をよりよいものにしようと常にあがき続けている。
そういう「もうちょっと悩んだほうがいいんじゃないの???」と突っ込みたくなるような、意図的にどこかが欠落したような妙な決意と楽観主義が、この作品を妙に乾いた希望が包む作品に仕上げています。『名探偵に薔薇を』のしっとりした悲壮感とは真逆でありながら、同じ「決意」を持っていることに、思わずニヤリ、でした。
世界観を変えるほどの傑作を生まない快作家。それでいいじゃないか。何が悪いんだ。それでいいんだ。
それがいいんだ。
「ちょっといい、が、かなりいい」
そんな城平京は、大阪市立大学の卒業生の中で、個人的ナンバー1!の先輩です!